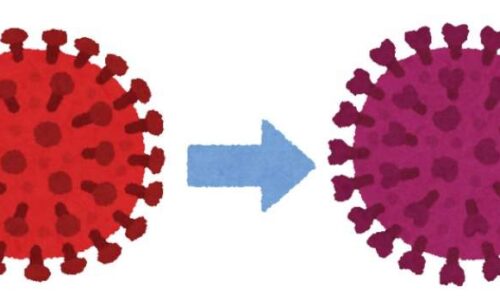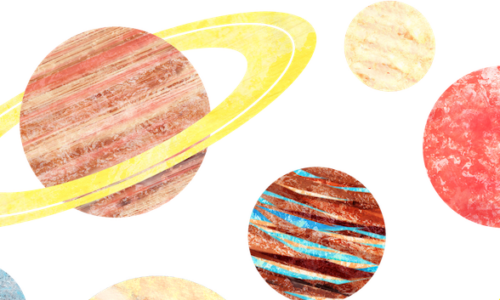童女のように茶目っ気のある人。この通り、スタジオでアイドルさながらの写真撮影もしてしまうぐらいノリもいい。

非公開の年齢を聞いて驚くが、さらに肩書きを聞くと、イメージと違っていて意外な気がしてしまう。
書道家大木ひさよ氏(号・水香、以下敬称略)、ストックホルム在住。こんなところに一流の日本文化の継承者を発見。
師、甫田鵄川
大木水香が、日本を代表する書家である甫田鵄川(ぼたしせん)の門をくぐったのは6歳の時。何事もやるからには一流でなければという両親が、大人でも弟子入りすることの難しい著名な書家を娘の師にあてがうために、相当な努力をしたという。
それ以来、水香は、甫田鵄川の愛弟子の一人として、2016年6月、甫田が92歳で胆のうがんで死去するまで師事した。死の直前まで筆を執っていた師の姿を思い浮かべながら、「最期まで、眼力の鋭い人だった」と水香は語る。
甫田鵄川 ぼた-しせん
1924-2016 昭和後期-平成時代の書家。
大正13年1月20日生まれ。木村知石に師事。昭和29年日展に初入選し,35年特選・苞竹(ほうちく)賞,44年菊華賞,平成5年内閣総理大臣賞。9年「菜根譚」で芸術院賞。王羲之(おう-ぎし)を中心に中国古典の研鑽(けんさん)につとめ,格調高い書をうちたてる。天真書道会を主宰。日展参事。奈良県出身。近畿大卒。本名は茂。
(出典、コトバンク)

※写真:91歳の時、生駒市長より市民功労感謝状を授与されている甫田鵄川。
(出典、生駒市市役所のホームページより。)
ストックホルムの書道教室
朗らかで気さくな人柄の水香のストックホルムの書道教室は、極めてリラックスした、ゆるいとも言える雰囲気で、水香先生主導による私語や談笑も珍しくない。大人も子供もスウェーデン人も混ざって、和気あいあいと書道をして、間にはティータイムまで入る。「さあ、みなさん。お茶にしましょうか。」と水香は、会場に持参の湯沸かし器を取り出し、毎回違う生徒の顔ぶれに合わせて準備した茶菓子を机に並べる。
子供が書いた習字は、「ほうら、みなさん、見てください。こんなに上手に書けましたよ。(パチパチパチ)」と”べた褒め”。子供は照れながらも嬉しそうに、張り切って練習を続ける。
でも先生、ちょっと甘すぎるんじゃありませんか。スウェーデンだからこうなんですか。
と率直に疑問をぶつけてみたところ、水香は、幼少期に、甫田鵄川に一度も叱られずに指導を受けたと言い、だからこそ楽しんで書道を続けてこれたのだと言う。
一流の師を持つということは、歯を食いしばって、涙を流しながらの修行を意味するのかと思いきや、必ずしもそういうものでもないらしい。
師の背中
甫田鵄川という”本物”の下で、自身は、叱られて、縮こまったりすることなく、伸び伸びと書の道を歩んだ。
他方、師が大人の弟子に向かって、「辞書は引いたのか」と一喝している光景も忘れてはいない。書道とは、たんに文字を書くことではない。文字の持つ意味や背景を十分に理解することが必須であり、書家は芸術家でありながら、同時に文字の学者でなければならない。
甫田鵄川は、水香が海外で日本文化の伝道者として活躍することを喜び、激励の意を込めた巻き手紙を持たせている。日本を離れてからの水香は、毎月、甫田鵄川に作品を郵送して指導を受けていた。頻繁に会うことこそできなかったが、短い電話での会話を通して、甫田鵄川の人生哲学をうかがい知ることもあった。
テレビを観ることもなく、最期まで、毎日、数種類の新聞に目を通すのが日課だった甫田鵄川は、生涯、向学心を持って学び続け、誰よりも自分に厳しかった。
高齢になっていた甫田鵄川は、たとえば風邪をひいても「風邪なんか引く方が悪いから。」と気丈に述べ、伏せることもなく、通常通り精力的に弟子の指導をしていたという。
そんな師の姿勢や生き方に感服しながら、大木水香は、甫田鵄川の弟子としての誇りを持って、ライフワークとしての書の道を歩み続けている。
書道では、テクニックに加えて、精神性なくしては作品にはなりえない。精神性を重視することが私にとっての書道であり、ゆえに書道は、私にとって人生の一部であると同時に根源である。by 大木水香
大木水香の教訓
一流に学べ
たとえば、水香が書道の指導をする上で、もっとも困るのは、字にヘンなくせのついている生徒だそうだ。「何事もやるからには、一流志向で。」という両親の態度は、そういう意味でも正しかったということになる。”安物買いの銭失い”に近いものかもしれない。
楽しく学べ
歯を食いしばり、涙を流して頑張る必要なし。楽しみながら道は極められるし、そうあるべき。
本物は、見る人が見ればわかる
筆を見たこともない外国人を相手にすれば、大げさに言えば、日本人なら誰でも習字の”先生”を名乗れる。あいうえおも知らない外国人相手なら、日本人の誰もが日本語の”先生”であるのと同じだ。玉石混淆の中、磨き抜かれた玉であることによる葛藤が生じないのかと問うと、「見る人が見ればわかる。」という回答が返ってきた。本物であることは、そう言える余裕があることなのだろう。

※右下の写真は、ストックホルム王立オペラ劇場の「マダム・バタフライ」のポスター。女の子の顔の朱文字が水香の書。

大木水香のサイト:https://www.calligraphyartist.net/(英語・スウェーデン語)
おまけ:父の娘

上の写真は、最近、大木水香の父が、娘のために誂えた着物の一部。辻が花の訪問着数枚に加賀友禅、鮫小紋、大島紬、エトセトラ・エトセトラとそれらに合う帯。父もまた、水香が日本文化の伝道者として活躍することを応援し続けた人物だ。
蝶よ花よと育てられてきた娘は、「着物はたくさん持っているから、欲しいなんて頼んでもないけれど、何枚あっても嬉しいわ」とニッコリする。甫田鵄川の愛弟子は、紛れもなくお父様の愛娘でもあるのだった。
おまけのおまけ:ホクオのひとりごと
子供の頃、近所の子供たちと一緒に、「そのへんの」先生のところで習字やピアノを習った。
シーンと静まり返った和室に正座して、黙々と練習した習字教室。楽しかったという記憶もない。
ピアノの方は、自分の順番を待っている間に、先生の家に置いてある漫画を読み漁るのが楽しみだった。クリスチャンの優しい先生で、時々、ドイツに旅行に行って、お土産には決まって、数色の色が混ざった色鉛筆をもらった。今、思えば田舎してはハイカラな先生だ。
中学に入るまで5年以上も毎週通って、結構、弾けるようになっていたつもりだったのに、大学に入って、趣味がてらにピアノの講義をとったとき、音大出のその先生に、「基本がまるでなっていない。手の形からしてまったくダメ。」とボロクソに言われて傷ついた。それ以来、人前で、ピアノが弾けるなんて絶対に言わない。
しかし、当時、あれらのお稽古事は、月謝がたったの2,3千円だったのではないだろうか。親が一流志向のかけらもなかったというのもあるが、一流の先生に教えを請うためには、親の財力がものを言う。そう考えると、ストックホルムの大木水香の書道教室は、ずいぶんお得である。